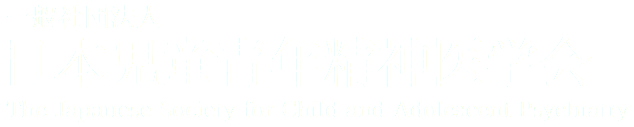機関誌
「児童青年精神医学とその近接領域」
Japanese Journal of Child and Adolescent Psychiatry
第65巻 第1号 2024年2月1日発行
第63回日本児童青年精神医学会総会特集(Ⅲ)
テーマ:こころの発達,それを支えるコミュニティ
シンポジウム7:神経発達症の生物学
| S7-1.神経発達症の神経心理学モデル | 岩渕俊樹 | 2 |
| S7-2.神経発達症の脳画像研究 | 幅田加以瑛 | 9 |
| S7-3.神経発達症に併存する概日リズム障害 | 高江洲義和 | 15 |
| S7-4.神経発達症の遺伝学的研究 | 高橋長秀 | 16 |
シンポジウム8:ギフテッドの子どもの支援
| S8-1.クリニックはギフテッドにどのように向き合うべきか─どんぐり発達クリニックでの実践─ 宮尾益知,佐藤俊一 |
18 | |
| S8-2.知能とは?ギフテッドとは?─ギフテッドの認知スキルと非認知スキル─ | 松浦直己 | 23 |
| S8-3.ギフテッドの現在までの認知科学的知見 | 池澤 聰 | 28 |
| S8-4.最新のテクノロジーを用いたギフテッドを有する方への支援 | 熊﨑博一 | 29 |
| S8-5.指定討論 | 杉山登志郎 | 30 |
シンポジウム9:「キレる」子どもに対する多職種による入院治療
| S9-1.怒りを受け止め続けた関わりにより,患児が課題を考えるきっかけとなった一例 千葉幸広,小川真彦,三ツ橋じゅん,佐藤竜也,佐藤徹也,青木絢子,牧野和紀,長尾眞理子 |
34 | |
| S9-2.臨床心理士の立場から若松病棟の「人垣」による育ちの「リフォーム」 ─暴言・暴力や反抗的態度が顕著だった小学男児の事例─ 中島直哉,三原勇樹,藤原真実,上田 望,礒邊顕生 |
39 | |
| S9-3.ソーシャルワーカーの立場から ─“集合会”(入院児の話し合いの場)における怒りの表現方法とソーシャルワーカーの関わり─ 堀内 亮 |
40 | |
| S9-4.児童精神科医の立場から─多職種による入院治療のポイント─ | 原田 謙 | 44 |
シンポジウム10:地域の特性に応じた神経発達症の子どもの支援体制づくり
| S10-1.発達障害児の地域支援システム簡易構造評価を用いた神経発達症のこどもと家族への支援体制 づくり 今出大輔 |
51 | |
| S10-2.沖縄県における地域支援体制づくりに向けた取り組みについて | 天久親紀 | 52 |
| S10-3.長野県の小規模自治体における支援体制づくりに向けた取り組みについて | 松田佳大 | 59 |
シンポジウム11:摂食障害の諸問題
| S11-1.摂食障害の社会的要因 | 千田真友子 | 67 |
| S11-2.摂食障害と家族問題 | 公家里依 | 70 |
| S11-3.摂食障害と自殺 | 吉村裕太 | 75 |
| S11-4.摂食障害と司法的諸問題 | 宮本悦子 | 75 |
子どもの人権と法に関する委員会パネルディスカッション:
生まれてくる子どもの権利─相模原事件とNIPT(無侵襲的出生前遺伝学的検査)を巡って─
| 当事者の立場から考える非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT) | 玉井 浩 | 84 |
| 高校生に対する無侵襲的出生前遺伝学的検査を教材とした授業実践から考える「子どもの人権」 森藤香奈子,松本 正,高尾真未,宮原春美,佐々木規子 |
85 | |
| 児童精神医学と優生思想:1970年代の学会活動再考 | 高岡 健 | 87 |
| 社会的養護経験者の自立支援の強化─改正児童福祉法について─ | 胡内敦司 | 90 |
| 未熟であることが,障害や罪にならない社会─「未熟」には養育を,「障害」には寛容さを─ | 早川 洋 | 91 |
| 社会的養護を離れても,こころの傷はまだ残っているのだということ | 陶山寧子 | 92 |
| 社会的養育におけるトランジションの課題─思春期の発達支援の再考─ | 小野善郎 | 93 |
| 指定討論 社会的養護における移行期の問題─精神科有床診療所の実践から─ | 佐藤順恒 | 94 |
教育に関する委員会セミナー:発達的な課題を持つ子どもへの新時代の教育システム
| 1.学校教育における児童生徒の1人1台の情報端末の活用 | 佐藤和紀 | 97 |
| 2.コロナ禍での発達障害児童の状況とICT教育 | 小野和哉 | 97 |
| 3.ICT教育導入の学校現場の現状と課題 | 小川文徳 | 99 |
倫理委員会セミナー:子どもとの秘密を守るということ
| 1.外来診療における子どもとの秘密にまつわる倫理的課題 | 庄 紀子 | 101 |
| 2.児童思春期精神科入院治療における子どもとの秘密をめぐる問題 | 中土井芳弘 | 103 |
災害対策委員会セミナー:コロナ禍における自閉症の子どもの居場所
| 1.コロナ禍における自閉症の子どもの居場所─医療機関での治療経験から─ | 田中恭子 | 105 |
| 2.コロナ禍における自閉症の子どもの居場所 ─コロナ感染者専用病棟を設置した精神科医療機関の立場から考えること─ |
田中 究 | 107 |
| 3.コロナ禍における自閉症の子どもの居場所─療育の現場から─ | 清田晃生 | 108 |
| 4.コロナ禍における自閉症の子どもの居場所─教育の現場から─ | 宮内かつら | 110 |
国際学会連絡・国際交流基金運営委員会セミナー:
Broadening Perspectives on Child and Adolescent Mental Health -New Frontiers of Research and Practice in Asia; ASCAPAP 2023へのお誘い
| 1.アジア児童青年精神医学会(ASCAPAP)への参加の意義 | 白瀧貞昭 | 113 |
| 2.ビデオレター(日本語要約) | 齊藤卓弥 | 115 |
| 3.アジア児童青年精神医学会(Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions: ASCAPAP)の活動紹介 |
金生由紀子 | 116 |
| 4.アジア児童青年精神医学会ASCAPAP2023 in Kyoto の企画にあたって | 岡田 俊 | 118 |
| 5.コメント 第1回アジア児童青年精神医学会 (Asian Society for Child and Adolesent Psychiatry and Allied Professions)の記憶 |
市川宏伸 | 119 |
薬事委員会セミナー:薬物療法の開始と終了─エビデンス,ガイドラインと臨床実践─
| ARMSを含む精神病性障害と抗精神病薬 | 藤田純一 | 121 |
| 神経発達症に対する抗精神病薬のエビデンスと薬物療法の適正化 | 岡田 俊 | 124 |
| ADHD治療薬 | 根來秀樹 | 126 |
| 抗うつ薬・気分安定薬(双極性障害に対する抗精神病薬を含む) | 宇佐美政英 | 128 |
| 睡眠薬・抗不安薬の薬物療法の開始と終了 | 辻井農亜 | 130 |
心理職に関する委員会セミナー:
医療領域で心理士はどうキャリアを形成するのか─現役大学院生が先輩心理士に聞く─
| 1.さまざまな職域の中で積む心理職としての専門性 | 早野留果 | 133 |
| 2.“しんりしょく”を考える | 齋藤真樹子 | 135 |
| 3.医療機関で働く心理職としてどういたいか/どういられるとよいか | 和田浩平 | 137 |
生涯教育に関する委員会セミナー:第12回臨床研究教育セミナー
| 臨床研究教育セミナーを終えるにあたり | 木村一優 | 139 |
| 臨床研究,もう一度基本に立ち戻って考えよう! ─PICO/PECOを復習して発展させましょう─ |
池之上辰義 | 140 |
| 児童・青年精神医学領域における研究の倫理 | 伊吹友秀 | 143 |
研究資料
| 療育手帳の交付児者を対象としたウェクスラー式知能検査と田中ビネー知能検査/ 新版K式発達検査の関連 村山恭朗,浜田 恵,明翫光宜,高柳伸哉,山根隆宏,小林真理子,内山登紀夫,辻井正次
|
147 | |
臨床経験
| 通園施設を不登園となった自閉症スペクトラム障害男児への行動論的アプローチ
浜田惠子,高橋雄一
|
162 | |
第63回日本児童青年精神医学会総会印象記
| 本田秀夫,冨田 哲,山室和彦,片桐正敏 | 184 |
書 評
| 一人ひとりに届ける福祉が支えるフランスの子どもの育ちと家族 安發明子著 | 清水將之 | 190 |
| ディスレクシア─ディスレクシアに関わる生物学的,認知的,環境的要因とは何か─ マーガレット・J・スノウリング著,関あゆみ監訳,屋代通子訳 |
柳生一自 | 191 |
| ラウンドテーブルトーク児童精神科医という仕事─臨床の過去・現在,そして明日を語る─ 岩垂喜貴編著,小平雅基,渡部京太,齊藤万比古著 |
太田豊作 | 192 |
編集だより
194