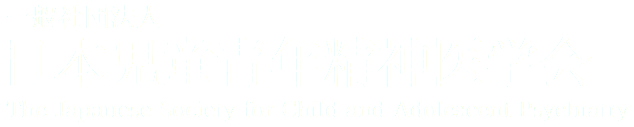一般社団法人日本児童青年精神医学会 定款細則
会員
第1条 正会員及び名誉会員は学術研究会への演題提出、機関誌への投稿への権利を有する。正会員、名誉会員及び団体会員は機関誌の配布を受ける。
第2条 正会員は代議員選挙の選挙権、被選挙権等の権利を有する。
会費
第3条 正会員は年度末日までに翌年度会費として10,000円の納入を必要とする。
2 正会員として新しく入会する者は入会金として2,000円の納入を必要とする。
3 名誉会員は年会費が免除される。
4 団体会員は年会費として15,000円の納入を必要とする。
第4条 学術研究会に出席する者からは参加費を徴収することができる。
会長
第5条 定款に定める役員のほかに会長をおく。
第6条 会長は学術研究会の準備、運営に当たる。
第7条 会長は代議員会において定める。
第8条 会長の任期は前学術研究会終了後より当該学術研究会終了後までほぼ1ヵ年とする。
理事
第9条 理事は就任の時点で満65歳を越えないものとする。
附則
この細則は平成26年2月16日より有効とする。
令和5年9月10日 改訂
一般社団法人日本児童青年精神医学会 会員の懲戒に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、定款第9条に基づき、当法人の会員(以下「会員」という。)に対し、懲戒における手続を公正に行うについて必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の対象となる行為)
第2条 理事会は、次の各号に掲げる行為をなした会員を懲戒することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反する行為
(2)当法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為
(3)当法人の会員の義務に違反し又は倫理綱領に反する行為であり、それが当法人の名誉および社会的信用に影響を及ぼすおそれがあると認められる行為
(4)法令に違反する行為であり、それが当法人の名誉及び社会的信用に影響を及ぼすおそれがあると認められる行為
(5)反社会的行為であり、それが当法人の名誉および社会的信用に影響を及ぼすおそれがあると認められる行為
(6)その他、当法人の社会的信用を失墜させると認められる行為
(懲戒の種類)
第3条
1 懲戒の種類は、以下の各号に掲げる通りとする。
(1)戒告 口頭にて将来を戒め、併せて戒告文書を交付する。
(2)会員資格の停止 相当な期間を定めて会員としての資格を停止する。
(3)除名 会員としての資格を喪失する。
2 会員資格停止となった会員は、会員資格停止の期間中についても当法人の会費を納入 しなければならない。
(懲戒に関する調査)
第4条 理事会は、第2条各号のいずれかに規定する行為をした疑いのある会員の存在が判明したときは、倫理委員会(以下「委員会」という)にその事実の有無、内容、程度、状況等を調査させなければならない。
(懲戒に関する手続)
第5条
1 理事会は、前条の調査結果に基づき、懲戒の要否、懲戒の種類、第3条第1項第2号の資格停止の場合はその期間を決定する。
2 会員を除名する場合は定款第9条に定める手続が必要である。
3 理事会は、会員に戒告、会員資格の停止を決定する場合は、あらかじめ当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4 弁明の機会の付与は、理事2名以上による聴聞又は書面の提出によるものとする。
5 聴聞は、その開催しようとする10日前までに、当該会員に対して、聴聞の日時・場所・聴聞する理由を記載した書面によって、通告しなければならない。
6 聴聞の通告を受けた会員が出頭拒否その他の理由で聴聞に応じないときは、理事会は聴聞をせずに懲戒することができる。
第6条 個別の懲戒事案の処理に関し本細則に定めのない事項については、理事会において決定する。
令和4年4月17日 作成
会員の懲戒における弁明の機会付与に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、定款第9条に基づき、当法人の会員(以下「会員」と言う。)に対し、懲戒を行う場合において、弁明の機会の付与に関する手続を公正・迅速に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(弁明の機会の主宰)
第2条
1 定款第9条に定める除名を行う場合の弁明の機会の付与については、代議員2名以上で行い、うち1名を弁明の手続を主宰する者(以下、「主宰者」という。)とする。但し、代議員間で主宰者は交替できる。
2 会員の懲戒に関する細則第3条第1項に定める戒告、または、会員資格の停止を行う場合は、理事2名以上で行い、うち1名を弁明の手続を主宰する者(以下、「主宰者」という。)とする。但し、理事間で主宰者は交替できる。
(主宰者の権限)
第3条 主宰者は、弁明の機会の付与に関する手続において、本細則に定めがない事項については、手続を公正・迅速に行うために必要な判断、措置を行う権限を有する。
(弁明の機会の通知の方式)
第4条 主宰者は、弁明の機会を付与するに当たっては、弁明の期日までに相当な期間をおいて、対象会員に対し、次に掲げる事項を書面により通知する。
(1)予定される処分の内容
(2)処分の原因となる事実
(3)弁明の期日および場所
(4)弁明の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類および証拠物(以下、「証拠書類等」と称す)を提出することができること
(5)主宰者が認めた場合、弁明の期日への出席に代えて弁明書および証拠書類等を提出することができること
(代理人)
第5条
1 対象会員は、主宰者が許可をした場合、会員の中から1名の代理人を選任することができる。
2 代理人は、対象会員のために、本細則で対象会員に認められた行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した対象会員は、書面でその旨を主宰者に届け出なければならない。
(参考人)
第6条 主宰者は、必要があると認めるときは、対象会員以外の者であって利害関係を有するものと認められる者に対し、参考人として当該弁明の機会付与に関する手続に参加することを求め、または当該弁明の機会付与に関する手続に参加することを許可することができる。
(審理の方式)
第7条
1 主宰者は、弁明期日の最初の期日の開始において、予定される処分の内容並びにその原因となる事実を、弁明期日に出席した者に対し、説明する。
2 対象会員または参考人は、弁明期日に出席して、意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。
3 主宰者は、弁明期日において、対象会員もしくは参考人に対し、質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を求めることができる。
4 主宰者は、対象会員または参考人の全部または一部が出席しないときであっても、弁明期日における審理を行うことができる。
5 弁明期日における審理は、公開しない。
(弁明書等の提出)
第8条 対象会員または参考人は、主宰者が認めた場合は、弁明の期日への出席に代えて、弁明期日までに弁明書および証拠書類等を提出することができる。
(続行期日の指定)
第9条
1 主宰者は、弁明期日における審理の結果、なお期日を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、対象会員および参考人に対し、あらかじめ、次回の弁明期日および場所を書面により通知する。ただし、弁明期日に出席した対象会員および参考人に対しては、当該弁明期日においてこれを告知すれば足りる。
(対象会員の欠席の場合における弁明の機会付与の終結)
第10条 主宰者は、対象会員が正当な理由なく弁明期日に欠席した場合には、弁明の機会の付与を終結することができる。
(弁明期日の調書および報告書)
第11条
1 主宰者は、弁明の機会の審理の経過及び内容の要旨を記載した調書を作成する。
2 主宰者は、弁明の機会付与の終結後、処分の原因となる事実に対する対象会員等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、前項の調書とともに代議員会または理事会に提出する。
(細則の変更)
第12条 この細則は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
令和4年4月17日 作成